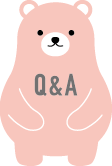大学キャンパスと社会的障壁
- ダイバーシティ
倉田賀世 ダイバーシティ推進室長


日本の法律は「障害者」をそれぞれの法律の中で定義しています。このうち、障害者の自立と共生を支援するための基本的な権利と義務を定める障害者基本法では、一定の機能障害があり、その「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」を「障害者」としています。ここでは、身体や精神に関わる機能障害だけでなく、これに伴う生活の困難さや社会参加への支障なども含めて広い意味で「障害者」を捉えているのが特徴です。このように「障害者」を捉えた場合、熊本大学のキャンパスにはどのような「社会的障壁」があるのでしょうか。今回、車椅子を利用されている工学部の中村先生と黒髪南キャンパスを歩いてみました。
車椅子の場合、通れる通路が限られるので、遠回りをしないと目的地にたどり着けない事がままあります。これに加えて、通路にでこぼこが多いため、中村先生曰く、サスペンションの効かない車椅子の場合、衝撃がかなり腰に来るそうです。さらに、自転車が建物入り口のスロープを塞いでいて通れないこともあるそうです。これについては、本推進室で黄色のポールを設置しました。この他にも、座ったままでは届かないエレベーターのボタン、重くて押せない入り口のドアなど、キャンパス内の社会的障壁は思っていた以上に高めです。このような状況について中村先生からは「キャンパス内の建物は、一つ一つ違います。比較的新しい建物のエレベーター、部屋の入り口は使いやすいですが、古い建物には一人では使用できないものが多いです。現在、私は部屋移動の際、事務職員の方などに付き添いやドアの開閉をお願いしています。」といったコメントを頂いています。
社会的障壁は自転車の置き方を考えるなど、ほんの少しの気遣いで低くすることも可能です。共生社会に必要な意識や知識の醸成も大学での重要な学びの一つであるとすれば、いかに社会的障壁に気づく事ができるのか、気づかせることができるのかが、私達に問われているように思います。